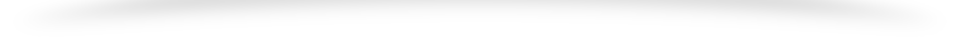「また液だれか…」
生産中止の札を前に、頭を抱えた経験はありませんか?
あるいは、「今日の液、なんだか機嫌が悪いな…」と、日によって変わる吐出量に首をかしげたことは?
製造現場でディスペンサと向き合う方なら、一度は経験する悩みだと思います。
こんにちは。
精密塗布のコンサルタントをしている、高城 賢治です。
かつて私も、廃棄される基板の山を前に眠れない夜を過ごしたエンジニアの一人でした。
しかし、ある時気づいたのです。
多くの不具合は、実はディスペンサの「設定ミス」や、良かれと思ってやっている「思い込み」が原因かもしれない、ということに。
この記事では、私自身が不良率を0.5%から0.01%へと激減させた経験を基に、ディスペンサの効率を最大化するための「液と対話する」5つの秘訣をお伝えします。
もう、一人で悩む必要はありません。
一緒に、安定塗布への道筋を見つけましょう。
Contents
秘訣1:圧力設定の罠 – 「強ければ良い」という幻想を捨てる
吐出が弱い、量が足りない。
そんな時、ついやってしまうのが「とりあえず圧力を上げてみる」という操作です。
気持ちは痛いほど分かりますが、実はこれが泥沼への第一歩だった、なんてことが現場ではザラにありますよね。
過剰な圧力は、バルブが閉じた後も液剤を押し出そうとするため、「液だれ」や「にじみ」の直接的な原因になります。
特にシリンジ内の液剤が満タンに近い時は、液剤自体の重み(水頭差)も加わるため、設定圧力以上に液が出やすい状態になっているのです。
では、どうすればいいのか?
答えは、液の表情をじっくりと観察することです。
まずは、今の設定から圧力を0.01MPaだけ下げてみてください。
そして、塗布された液の輪郭や高さを観察するのです。
次に、逆に0.01MPaだけ上げてみる。
この微細な変化の中で、液が最も「素直な顔」を見せる瞬間が必ずあります。
それが、あなたの現場における最適圧力の出発点になるはずです。
秘訣2:温度管理の死角 – 液剤は正直な「生き物」である
「工場は空調で24時間、温度管理しているから大丈夫」
そう考えているとしたら、少し危険なサインかもしれません。
液剤というのは、私たちが思う以上に正直な「生き物」です。
特に粘度は温度に非常に敏感で、一般的に温度が1℃変わるだけで、粘度は数%も変化してしまいます。
例えば、朝一番の少しひんやりした空気の中で設定を出したディスペンサが、昼になって気温が上がると、粘度が下がって(サラサラになって)吐出量が増えすぎてしまう。
これは、液剤の“機嫌”が温度によって変わってしまった典型的な例です。
ここでの腕の見せ所は、いかに「液剤のご機嫌を一定に保つか」です。
シリンジウォーマーなどを活用して液剤自体を温め、常に一定の温度に保つのが理想ですが、すぐに導入できない場合もありますよね。
そんな時は、休憩時間にシリンジをどこに置くか、少しだけ工夫してみてください。
機械の排熱がある暖かい場所や、逆に冷風が当たる場所を避けるだけでも、液剤の温度変化はかなり緩やかになります。
液剤を、気まぐれなパートナーだと思って優しく扱ってあげることが、安定稼働への近道なのです。
秘訣3:ノズルの選定 – 「神は先端に宿る」を実践する
装置を購入した時に付属してきた標準ノズルを、ずっと使い続けていませんか?
もしそうなら、あなたは最高のパフォーマンスを発揮できるF1マシンに、市販のエコタイヤを履かせているようなものかもしれません。
私の信条の一つに、「神は細部に宿り、液は先端に宿る」という言葉があります。
ノズルは単なる出口ではなく、塗布品質の9割を決めると言っても過言ではない、心臓部です。
例えば、粘度の高い(ネバネバした)液剤に、細く長いストレート形状のノズルを使うと、内部の抵抗が大きすぎてスムーズに吐出されず、脈動や吐出量不足の原因になります。
こういう場合は、根本が太く、先端に向かって細くなるテーパー形状のノズルを選ぶことで、液剤はストレスなくスムーズに流れてくれるのです。
材質も重要です。
液剤によっては金属と反応してしまうものもありますし、微細な塗布には先端がシャープな金属ノズルが、糸引きしやすい液剤にはテフロン製のノズルが有効な場合もあります。
一度、あなたの使っている液剤の特性とノズルの仕様を、じっくり見比べてみてください。
きっと、新しい発見があるはずです。
秘訣4:液剤の準備 – “ひと手間”が安定稼働の分かれ道
最高の料理人が、最高の食材のポテンシャルを最大限に引き出すために「下ごしらえ」に時間をかけるように、ディスペンサの安定稼働も「液剤の準備」というひと手間で大きく変わります。
よくあるのが、冷蔵庫で保管していた液剤を、現場に来てすぐに装置にセットしてしまうケースです。
冷たくて硬い状態の液剤は、本来の性能を発揮できません。
最低でも使用する1時間前には冷蔵庫から出し、室温にしっかりと馴染ませてあげましょう。
また、液剤の中にフィラー(機能性を持たせるための粒子)が含まれている場合、長時間静置しておくと沈殿してしまいます。
これでは、塗布する場所によって成分が変わってしまい、品質が安定するはずもありません。
使用前には必ず、攪拌機や自転・公転ミキサーで均一に混ぜてあげてください。
そして、意外と見落としがちなのが「気泡」です。
液剤をシリンジに移す際や攪拌時に巻き込まれた小さな気泡は、吐出途切れや量バラつきの最大の敵。
必ず脱泡機(遠心分離機など)にかけて、液剤が最高のパフォーマンスを発揮できる状態に整えてあげましょう。
この“ひと手間”が、後々のトラブルを未然に防ぐ最大の防御策になるのです。
秘訣5:「水頭差」との対話 – 残量が減っても慌てない技術
「シリンジが満タンの時と、残量が少なくなった時で吐出量が変わってしまう…」
これは、多くの現場担当者を悩ませる、非常に根深い問題です。
この現象の正体は、主に「水頭差」。
難しく聞こえるかもしれませんが、要するに「2リットルのペットボトルから水を注ぐ時、満タンの時の方が少しの傾きでドバっと水が出やすい」のと同じ原理です。
シリンジ内の液剤の自重が、設定圧力にプラスして働いてしまうのですね。
最新のディスペンサには、この水頭差を自動で補正してくれる機能を持つものもあります。
しかし、そうした装置に頼る前に、私たちにできることはたくさんあります。
例えば、生産開始時の「満タン設定」、中間時点の「半分設定」、終了間際の「少量設定」というように、残量に応じた吐出設定を複数パターン用意しておくのも一つの手です。
あるいは、もっとアナログに、残量ゲージを見ながら、少なくなってきたら手動で圧力を0.01MPaずつ上げて微調整していく。
一見、非効率に見えるかもしれません。
しかし、こうして液剤の残量と向き合い、対話しながら調整する経験こそが、あなたの中に「生きたノウハウ」を蓄積させてくれるのです。
まとめ
今回は、ディスペンサの効率を最大化するための5つの秘訣についてお話ししました。
- 圧力設定: 「強ければ良い」ではなく、0.01MPa単位で液の表情を見る。
- 温度管理: 液剤は「生き物」。温度を一定に保ち、ご機嫌を損ねない工夫を。
- ノズル選定: 「神は先端に宿る」。液剤の特性に合った最高のパートナーを選ぶ。
- 液剤の準備: 使用前の「下ごしらえ」を惜しまない。常温戻し・攪拌・脱泡は必須。
- 水頭差との対話: 残量による変化を理解し、設定の微調整で乗りこなす。
いかがでしたでしょうか。
小難しく聞こえたかもしれませんが、全ては「液と対話する」という、たった一つのシンプルな心構えに行き着きます。
焦らず、騒がず、液と対話する時間を取りましょう。
まずは、お手元のディスペンサの温度計を見てみてください。
あるいは、ノズルの先端をじっくりと観察してみてください。
きっと、液の表情が昨日とは違って見えるはずです。
そこから、あなたの現場の品質向上は始まります。
最終更新日 2025年11月28日 by unratt